「教科書が読めない子ども」とは、あなたのことですよ
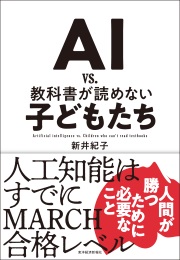 NIIの新井紀子先生の「AI VS. 教科書が読めない子どもたち」を読みました。遅読の私にしては珍しく、今月発売になったばかりの本をその月の間に買い、半日ほどで読了しました。
NIIの新井紀子先生の「AI VS. 教科書が読めない子どもたち」を読みました。遅読の私にしては珍しく、今月発売になったばかりの本をその月の間に買い、半日ほどで読了しました。
新井先生が代表となって取り組まれている基礎読解力テストについては、このブログでもたびたび取り上げております。中学校の数学・社会・理科の教科書の文章や、新聞の科学面や子ども向けの記事を題材として読解力を測るテストを実施したところ、中学生の約半分は正確に内容が読み取れておらず、3割は主語・述語・修飾語の係り受けや指示語が指している内容も把握していないことが分かったというニュースをご覧になった方も多いでしょう。
今回の調査の対象の多くが中学生や高校生だったために、「教科書が読めない子どもたち」と言われていますが、ここ数年の中高生の読解力だけが急激に落ちたということもないでしょうから、国民全体の読解力も、同様に危機的な状況にあるのではないかと本書では指摘されています。
基礎読解力テストは、
①主語・述語・修飾語などの「係り受け」
②指示語の内容(「照応」)
③同じような単語が使われた二つの文を比べて、それらの意味が同じか違うかを判断する「同義文判定」
④自分の知識経験を使って何が書かれているか理解する「推論」
⑤文章の内容と一致する図を選ぶ「イメージ同定」
⑥定義を読んでそれと合致する具体例を認識する「具体例同定」
の、読解に関する6つの力を測れるようになっているそうです。
この中で①と②、「係り受け」と「照応」は、AIでもかなりの精度で正解できるそうです。人間の中学生でも7割方はできる(逆に3割はできないのですが・・・)。
しかし、③~⑥は、コンピュータにはなかなか難しい課題なのだそうです。新聞などでも紹介された問題ですが、
A 幕府は、1639年、ポルトガル人を追放し、大名には沿岸の警備を命じた。
B 1639年、ポルトガル人は追放され、幕府は大名から沿岸の警備を命じられた。
この2文の意味が同じか違うか、コンピュータにはなかなか判断が付かないそうです。なぜなら、コンピュータはつまるところ言葉の意味を理解することができないので、これらの文のように使われている単語がほとんど同じになると、判断のしようがなくなってしまうからだそうです。
問題は、人間もAIと同じような間違いをしてしまっていることにあると新井先生は指摘しています。
上の分野の中で、AIの苦手な③~⑥の問題を人間がちゃんと解けるのであればよいのですが、人間も当て勘で選んだ程度でしか正答できていないことが、このテストで明らかになりました。
私たちの子どもたちが大人になるころには、今ある仕事の多くがAIにとってかわられたり、必要とされなくなる一方で、新しい仕事が誕生するだろうと言われています。もし今ある仕事がなくなって職を失った人々が、新たに誕生した仕事に再就職できるのであれば、それは大した問題ではありません。
しかし、どうでしょうか。AIにとってかわられた仕事から駆逐された人々が、AIでも出来るような能力しか持ち合わせていないとしたら。そのような人々は、せっかく新しく生まれた仕事を遂行する能力のある者とは認められず、結局失業したままか低賃金労働をいくつも掛け持ちするような状況に陥ることになるのではないでしょうか。
そのようななかなか恐ろしいことが予言されています。実際、過去の歴史においても同じようなことが起こったことも指摘されています。
20世紀初頭、工場のオートメーション化が進み、多くの工場労働者が職を失いました。そのころは新たにホワイトカラーの仕事が生み出された時期でもあるのですが、工場を追い出された労働者たちは、ホワイトカラーの労働力として吸収されることはありませんでした。なぜなら彼らにはそれに必要な教育を受ける機会がなく、能力を持ち合わせていなかったからです。結果、世界恐慌の遠因ともなった大量の失業者が生み出されてしまいました。
AI技術の進歩で、近い将来にそのようなことが起こるだろうと、本書では予言されています。
さて、それではこのような時代にはどのような能力が大切かということになってきますが、それはやはり読解力であろうということです。近い将来、今の子どもたちがテスト前に一夜漬けで詰め込んでいるような知識が全く役に立たなくなるような時代が来るとしても、読むことができる人間であれば、インターネットやメディアの情報を読み取って、何をするべきかを自分で判断できるだろうからです。
この辺で、国語道場という塾を主宰している私の問題意識と一致してくるわけですね。
国語道場という塾は、教科としての国語の成績を上げるための授業「も」やっています。中間期末テストで国語でよい点を取れるようにしたり、実力テストの国語で高い偏差値をとれるようにしたりする指導ですね。
しかし、それ以上に重要なのは、あらゆる学びの基盤となる日本語能力としての「国語」の指導だと思っています。
具体的には、読書指導「ことばの学校」、国語記述の小学生向け2科目で、これを実践しています。
読書指導「ことばの学校」は、約300冊の良書から、一人一人の現状の日本語語彙力にあったレベルの本を読み進めさせ、効果的に読みの正確さや日本語語彙力を向上させることができます。このことは、年に2回実施される「読書指数診断」というテストによって実証されています。
国語記述という科目は、将来の高校入試や大学入学共通テスト、国立大学2次試験の記述問題に通じる、国語の記述力を育てる学習指導です。文法や慣用句・熟語などの知識を学び、読解問題演習ではすべて解答を記述式で書かせます。文章から読み取ったことを、他人に理解できるように答案を書く練習を積ませるわけです。
これらのことは、単にその時その時の国語の成績を上げるというだけの目的で行っているのではありません。全般的な学力の基礎力を向上させることが最大の目標です。これからの世の中で起こる変化を生き抜くために必要な力を向上させることができると思っています。
もちろん、あらゆる学びの基盤としての国語力をつけることは、当面の定期テストや実力テストでよい成績をとり、入試で志望校に合格することにも当然役に立つのですがね。
—————
お問い合わせ先
国語道場(西千葉)稲毛区緑町1丁目27-14-202
千葉市
263-0023
043-247-7115
お電話のお問い合わせは、火~土曜日の午後3時~9時
メールは24時間承っております。
